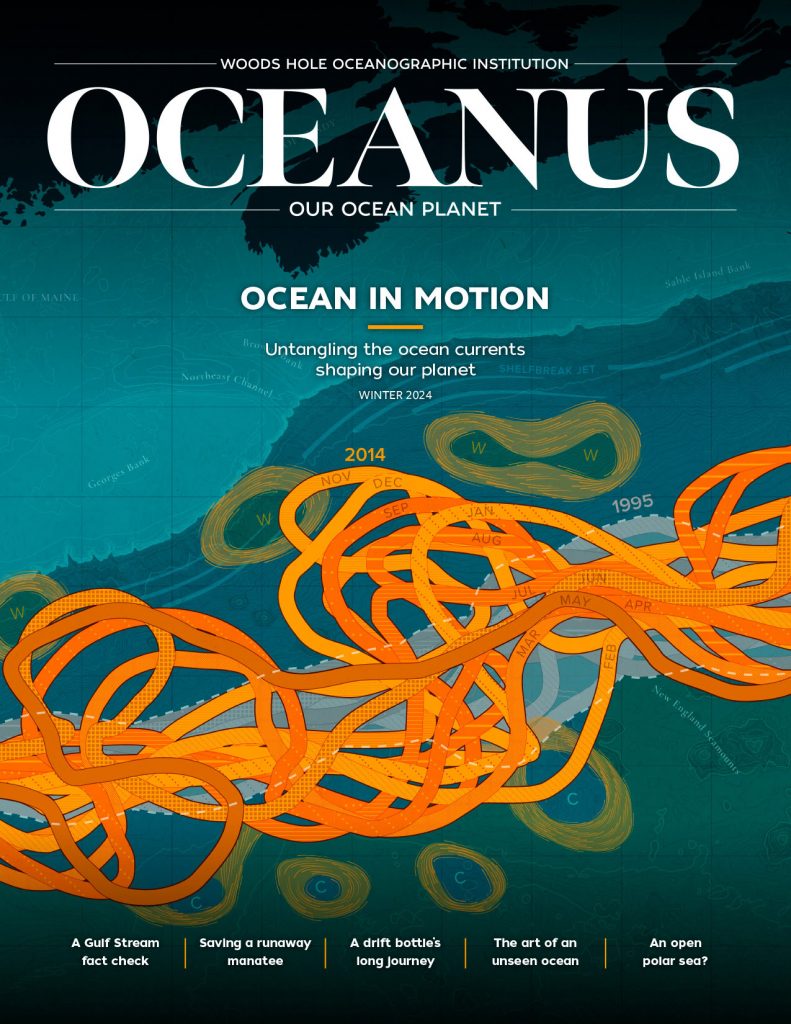海洋生物への影響
福島の原発事故によって、前代未聞の量の放射能が短期間で海域に流出した。セシウムその他の放射性物質体が断続的に流出することで、海洋生物の食物連鎖はどのように影響を受けたのだろうか。2012年11月の「海洋放射能汚染に関する国際シンポジウム」で、それについての基礎的な資料を提供したのがスコット・ファウラー教授である。彼は、海洋放射線生態学の先駆者として国際原子力機関海洋環境研究所(IAEA-MEL)で30年以上勤務してきた。
食物連鎖は、海洋植物プランクトンから始まる。これは微小な植物であり、その光合成量は陸上の植物全体の光合成量と同程度にもなる。海洋植物プランクトンは周囲の海水から放射性汚染物質を取り込む。そして、植物プランクトンが、より大きな動物プランクトンに摂食され、さらに小型魚類、そしてより大きな生物へと食物連鎖のピラミッドをのぼっていく。それにともない、汚染物質の一部は最終的に海底に堆積するそれら生き物の糞その他からなる「デトリタス粒子」に含まれることになる。デトリタス粒子は堆積物に蓄積し、それに含まれる放射性核種(放射性物質)の一部は、微生物および化学過程を通じて上層の水中へと再び移動する場合もある。
海洋生物にどのくらいの放射能が取り込まれるかには、さまざまな要因がある。もちろん、生物が放射能にさらされる時間の長さは重要である。さらに、生物の大きさと種、関与する放射性核種、水温と塩分、水中の酸素量、生物の成長段階など、多数の要因も重要である。
また、「自然バックグラウンド放射線がもともと海のいたるところにあるのを忘れないことです」と彼は言う。例えば、ポロニウム210とカリウム40は海中で自然発生する放射性核種である。カリウム40は海中に最も豊富に存在する放射性核種であるが、ポロニウム210の方がカリウム40よりも海洋生物内に蓄積しやすい。
「魚類その他の海洋生物が受ける放射線量の大半は、ポロニウムによるものです」。
ファウラーは放射性同位体が海水から海洋生物に吸収されるという第1の経路に関し、1980年代初期の実験において、プルトニウム量には生物の分類群によって非常に大きな差があることを実証した。植物プランクトンは、微小動物プランクトンの約10倍プルトニウムを蓄積し、微小動物プランクトンは、二枚貝の100倍プルトニウムを取り込んでいた。タコとカニのプルトニウム取り込み量は二枚貝の約半分だったが、海底近くに生息する魚類よりも約100倍大きかった
また、環境に存在する放射性核種ごとに、各生物で異なる取り込み量が示された、と彼は言う。
放射性同位体が堆積物から海洋生物へ移動する第2の経路は、複雑なものである。ファウラーによると、アメリシウムの取り込み量を測定した実験では、汚染堆積物にさらされた蠕虫は二枚貝より有意に多くの放射性同位体を取り込んだ。ただし、蠕虫も二枚貝も、炭素鉱物を多く含む大西洋の堆積物より、シリカ鉱物を多量に含む太平洋の堆積物からはるかに多くの放射性核種を取り込んだ。
第3の経路である食物は、場合によっては、最も重要な取り込み因子になる。摂取された放射性同位体は消化器を通じて体内に同化されるが、これは体外環境から吸収された場合より、はるかに効率の良い経路である。ファウラーによれば、特に海底近くに生息するヒトデやウニなどの海洋無脊椎動物は、摂取した広範囲な放射性同位体を効率的に吸収する。だが、幸いなことに取り込んだ放射能は排泄され、次第に失われていく。
プランクトンからマグロへ
ファウラーの長年の研究仲間であるニコラス・フィッシャー教授は、福島で最も大きく影響をおよぼした同位体に焦点を絞った。フィッシャーはストーニーブルック大学放射性の海洋生物地球化学者で、海洋生物における金属と放射性同位体の行き先を35年間にわたって研究している。その研究対象には放射性廃棄物に伴う放射性核種も含まれている。彼と研究室メンバーは、2011年6月、ウッズホール海洋研究所のシニアサイエンティストである海洋地球化学者ケン・ベッセラー博士が中心となって日本の沖合で行った調査航海に加わった。
試料として採取したプランクトンと魚を分析したところ、一貫してセシウム134とセシウム137が見つかった。福島第一原発事故でセシウムとともに多量に流出した放射性核種であるヨウ素131は、当然のことながら見つからなかった。「ヨウ素131は半減期がわずか8日であるため、事故から2か月後には検出できなくなっていました」とフィッシャーは説明する。
セシウムはまた別の問題である。1960年代の冷戦時代、大気圏内で行われた核実験に端を発するセシウム137は、海とそこに生きるものたちに今なお痕跡を残している。それに比べてセシウム134ははるかに短命であるが、それでも数年は存在し続ける。
セシウムは、海水に豊富に含まれる非放射性セシウム、そして自然発生するカリウムとナトリウムなど、いくつかの可溶性同位体と競合して、生物および粒子に吸収される。海水と比べ、淡水ではカリウムおよびナトリウム同位体がはるかに少ないため、セシウムの取り込み量は海洋生物より淡水生物の方がいちじるしい。 セシウムの化学特性はカリウムと似ており、どちらも最終的には魚類その他の海洋生物で同じ組織、特に筋肉組織に含まれる。
また、魚類はかなり効率的にセシウムを排泄し、1日あたり数%を失う。そのため、魚類は新たな汚染源にさらされなければ、体内のセシウム濃度は時間とともに急速に低下する。
高次捕食生物において特に懸念されるのは、食物連鎖のピラミッドを上にのぼるにつれて放射性核種の濃度が高まることである。これを生態学者は「生物学的濃縮」と呼ぶ。この場合もやはり幸いなことに、「海洋の食物連鎖におけるセシウムの生物学的濃縮はさほどではなく、水銀、農薬のDDT、ポリ塩化ビフェニル(PCB)など多くの有機化合物よりははるかに低いです」とフィッシャーは述べる。
2011年の航海で、フィッシャーとそのチームは採取した全試料についてセシウムを測定した。その試料は主に動物プランクトンで、一部は魚類である。予測にたがわず、試料採取した生物のセシウム濃度は、沿岸に近づくほど高まった。また、放射性の銀110mもすべての動物プランクトン試料で検出された。ただし、すべてのケースでセシウムおよび銀同位体の量は同じ試料中の自然発生カリウム40よりいちじるしく低かった。
「私たちが採取・分析した魚類の放射能では、人が摂取しても問題を生じることはありません」が、同じ海域で水揚げされる他のすべての海洋生物にも同じことが言えるとは限らない、と彼は付け加えた。
通常より高濃度が持続している
フィッシャー、ベッセラー、その他多くの科学者が頭を悩ませている問題がある。それは、低量ではあるが有意な濃度の放射能がいまも海中に存在し続けていることである。東京海洋大学の海洋化学学者、神田穣太教授は、福島近海を広範囲にわたって調査し、水深200mより浅い沿岸水域とその海底の堆積物に今なお存在するセシウムの量を算定した。神田の計算では、残留量は全排出量の3%未満で、残りはかなり以前に外洋へ流されている。
それでも、セシウム放射性同位体はこの海域で1m2あたり数十~数百ベクレルと測定されており、これは福島災害以前の濃度よりいちじるしく高い。さらに、より重要な点として、沿海の堆積物および数種の魚類で測定された濃度は周辺海域の濃度より高い。
この高い放射能には、3つの源があると神田は見る。1つは河川からの流出、つまり雨で近くの河川に流された放射性降下物が海に流出したもの、である。2つめは、原子炉建屋の地下から今も少量の汚染水が漏れ続けているのではないか、と神田は示唆する。しかしながら、いまだ魚類の組織で測定され続ける放射性セシウム濃度についての唯一妥当な説明は、魚が食物を通じて継続的に放射性セシウムを摂取していること、である。その疑いは3つめの海底の堆積物に向けられている、と神田は言う。
神田は、「沿海堆積物に合計95テラベクレル(1012ベクレル)のセシウムが存在すると推定し、それがどのようにしてそこにたどり着いたかが問題です」と言う。セシウムは水面でプランクトンに摂取され、糞粒として海底へ沈んでいっている可能性がある。実際、浅水域のプランクトンが高濃度のセシウムを呈することはある。また、河川から流されてきた有機物の小片とともに海底に到達している可能性もある。一方で、汚染水に接触した粘土粒子にセシウムが吸着した可能性もあるが、そのような放射性セシウムは粘土粒子に強く結合するため、海洋生物には取り込まれにくい。
堆積物は複雑なものである。一粒の砂のように見えても、間近で見ると、たいていは鉱物、有機物、および間隙水(粒子間の小さなすき間を満たしている水)の混合物である。これら凝集体への汚染物質取り込みについては、よくわかっていない。ファウラー同様、神田も、「堆積物の組成と特性は場合によって大幅に異なっています」と言う。
このなくならない放射能の謎を解くには、福島沿岸域の海底を徹底して分析する必要がある。「地域の住民は心配しています。いつになったら漁業を再開できるのか知りたがっています。私たち科学者は、それに答えなければなりません」。
この謎を解く鍵は、いつまでセシウムが居座り続け、どのような経路で食物連鎖に取り込まれるかにある。セシウム137の半減期が30年であることを考えると、これからの数十年間、海底堆積物が食物連鎖の汚染源となり続けるおそれがある。